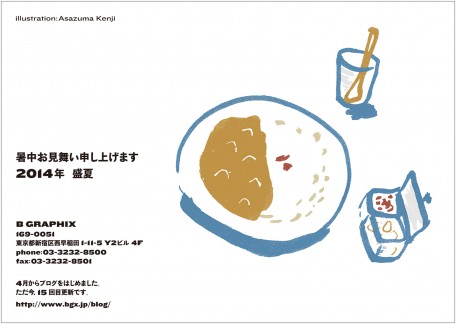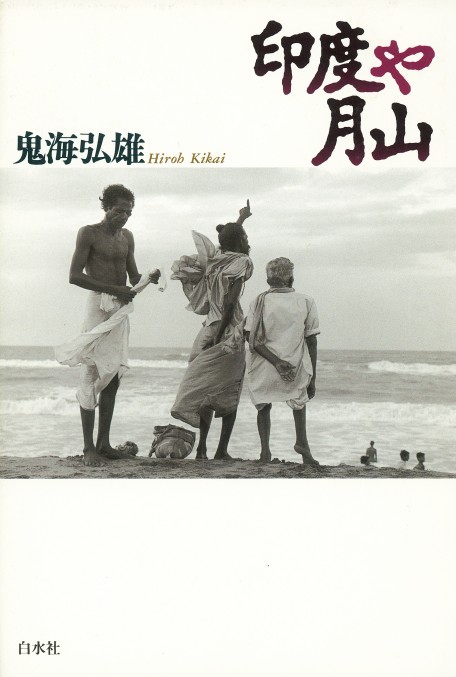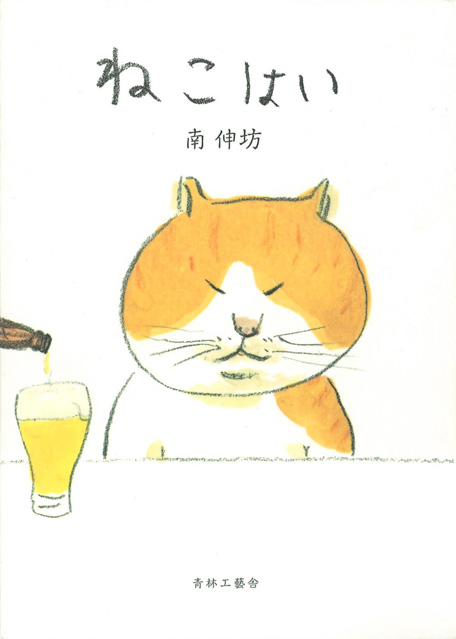またまた、サッカーワールドカップの話ですみません。
週刊新潮(7月31日号)の連載コラム「管見妄語』で、藤原正彦さんが私と同じ意見だ。
〈日本の致命的欠陥はここ五十年間、何はさておき守備陣のダッシュ力欠如だ。すぐに相手に振り切られてしまう。世界の速いフォワードは五十メートルを六秒そこそこで走る。六秒五のバックスでは十メートル並走しただけで八十センチも先に出られてしまう。勝負にならない。そして何より、ダッシュ力に自信がないと敵の逆襲が恐いからいつも後方に引き気味となる。前線と最終ラインとの間を狭く保つコンパクトサッカーができないのだ。(略)優勝したドイツは最もコンパクトサッカーに徹していた。日本代表の守備陣は、五十メートルを少なくとも六秒前半で走れる者のみにしないといけない。半ば生まれつきの能力だからかほとんど触れられないが、守備陣のダッシュ力がないかぎり、いくら監督や作戦を変え、いくら技術やチームワークを向上させようと、永遠に世界には太刀打ちできないのだ。〉
Read More